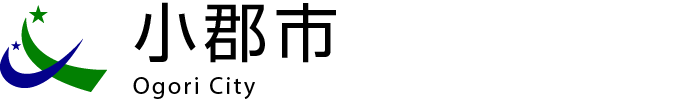経済支援
- 1
奨学金制度
-
小郡市奨学金(井手奨学金)
市では、故井手宗夫氏からの寄付金を活用し、平成13年度より奨学資金の給付制度を設け、経済的理由によって修学困難な生徒に対して奨学資金の給付を行い、社会に貢献しうる人材の育成を図ってきました。
この奨学金は、平成25年11月の申込みをもちまして、終了しました。
なお、公益財団法人福岡県教育文化奨学財団が実施する奨学金については、福岡県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
- 2
就学援助制度
-
小郡市では、経済的な理由によって給食費や学用品費の支払いにお困りの小・中学校の児童生徒の保護者に対して、その費用の一部を援助する就学援助制度を設けています。
就学援助は、年度ごとに申請が必要です。令和6年度に就学援助費を受給していた方も、引き続き援助を希望する場合は、令和7年度分の申請を行ってください。年度の途中でも申請していただけます。
なお、令和7年度の新入学者で、令和7年2月に入学準備金の認定を受けた方は、再度申請する必要はありません。ただし、小2~小6、中2~中3の兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹分の申請を行っていただく必要があります。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響も含め収入が減少し、学用品費等のお支払いにお困りの世帯については、小郡市教育委員会 教育総務課 教育総務係までご相談下さい。(ご相談は令和8年2月末まで受け付けます。)就学援助の対象となる世帯
(1)市民税が非課税の世帯
(2)国民年金の保険料や国民健康保険が免除されている世帯
(3)児童扶養手当を受給している世帯
(4)その他、生活保護に準じる程度に生活が苦しい世帯(※別表を参考にしてください)<別表>令和7年度就学援助認定における収入の目安 世帯構成(モデル) 世帯収入の目安(年収) 3人世帯(持家の場合)
父35歳、母35歳、小7歳2,670,000円 3人世帯(借家の場合)
父35歳、母35歳、小7歳3,354,000円 4人世帯(持家の場合)
父50歳、母39歳、中14歳、小10歳3,540,000円 4人世帯(借家の場合)
父50歳、母39歳、中14歳、小10歳4,212,000円 5人世帯(持家の場合)
父38歳、母36歳、小10歳、小8歳、小7歳4,080,000円 5人世帯(借家の場合)
父38歳、母36歳、小10歳、小8歳、小7歳4,758,000円 6人世帯(持家の場合)
祖父75歳、父48歳、母42歳、中14歳、中13歳、小11歳4,590,000円 6人世帯(借家の場合)
祖父75歳、父48歳、母42歳、中14歳、中13歳、小11歳5,304,000円
※金額は、社会保険料・生命保険料・地震保険料・市民税控除後のものです
※金額は、あくまで目安であり、家族構成(人数・年齢)等によって大幅に異なる場合があります
援助の内容
給食費、学用品費、入学準備金、修学旅行費、オンライン通信費、医療費 など
※医療費は、学校保健安全法で定める以下の疾病が対象です
(1)トラコーマ、(2)結膜炎、(3)白癬(たむし、しらくも、水虫)、(4)疥癬(伝染の皮膚疾患)、(5)濃痂疹(とびひ)、(6)中耳炎、(7)慢性副鼻腔炎、(8)アデノイド、(9)う歯、(10)寄生虫病(虫卵保有を含む)申請に必要な書類
就学援助の申請には、以下の書類の提出が必要です。
(1)就学援助申請書(下記「申請フォーム」から申請される場合は不要です。)
(2)課税所得証明書など(※該当者のみ提出)
※(1)就学援助申請書は、お子さまが通っている学校又は小郡市教育委員会教育総務課に準備しています。また、以下からダウンロードすることもできます。
※就学援助の認定に当たっては、世帯員全員の収入や市民税額等の情報が必要です。税の申告がされていないと審査することができませんので、ご注意ください
※市外からの転入者については、転入時期によって、(2)課税所得証明書など(収入・社会保険料・生命保険料・地震保険料・市民税額が記載された証明書)の提出が必要です。別表でご確認ください≫就学援助申請書(PDF:110KB)
就学援助申請書記入例(PDF:129KB)<別表>令和7年度の就学援助申請 申請時期 課税所得証明書などの提出が必要な方 提出が必要な書類 令和7年5月末まで 令和6年1月2日以降に小郡市に転入した方 令和6年度の課税所得証明書など 令和7年6月以降 令和7年1月2日以降に小郡市に転入した方 令和7年度の課税所得証明書など 申請方法
申請に必要な書類をそろえて、お子さまが通っている学校又は小郡市教育委員会教育総務課に提出していただくか、申請フォーム(外部リンク)から申請してください。
- 課税所得証明書などの提出が必要な場合は、お子さまが通っている学校又は小郡市教育委員会教育総務課に提出してください。
- 年度途中の申請も可能です。(転校・転入・世帯の状況の変化以外は令和8年2月末日に申請を締め切ります。)年度途中から認定された人は、認定された月以降からの月割り支給になります
支給方法と支給時期
就学援助費は、お子さまが通っている学校を通じて、学期ごとにまとめてお支払いします。支給時期は、7月・12月・3月です。
就学援助ポータルサイト
就学援助制度について詳しくは、文部科学省のウェブサイト内「就学援助ポータルサイト」(外部リンク)をご覧ください。
- 3
就学援助費(入学準備金)の入学前支給のお知らせ
-
小郡市では、経済的な理由によって給食費や学用品費の支払いにお困りの小・中学校の児童生徒の保護者に対して、その費用の一部を援助する就学援助制度を設けています。
小・中学校の1年生を対象とする入学準備金は、入学前の3月に支給します。入学準備金の入学前支給を希望される方は、次のとおり申請してください。
なお、新入学者以外の学年の児童生徒については、令和8年3月以降に申請を受け付けます。入学準備金の入学前支給を受けることができる方
就学援助を受けることができる世帯のうち、次の要件すべてに該当する方です。
- 令和7年12月に小郡市に居住している方
- お子さまが令和8年4月に小・中学校(小郡市以外の市町村立小学校を除く)に入学する方
- お子さまの入学までに小郡市外へ転出される見込みがない方
申請方法
- (1)書類申請
- 小学校新入学者の場合
小郡市教育委員会 教育総務課 教育総務係(市役所 西別館3階)で、令和7年12月19日(金曜日)までに申請してください。 - 中学校新入学者の場合
令和7年度にお子さまが就学している小郡市立小学校で、令和7年12月下旬の各学校が指定する日までに申請してください。申請期限は学校を通じてお知らせします。
- 小学校新入学者の場合
- (2)電子申請
申請フォーム(外部リンク)から令和7年12月19日(金曜日)までに申請してください。
- 申請期間が終了した後は、入学後に申請することができます。この場合、入学準備金の支給時期は令和8年7月以降になります。
- 課税所得証明書などの提出が必要な場合は、お子さまが通っている学校又は小郡市教育委員会教育総務課に提出してください。
申請書類
就学援助申請書
申請手続に必要なもの
令和7年度の課税所得証明書など(該当者のみ提出)
- 就学援助の判定には、世帯員全員の収入や市民税額などの情報が必要です。税の申告がされていないと審査することができませんので、ご注意ください
- 令和7年1月2日以降に市外から転入した世帯員については、令和7年度の課税所得証明書など(収入・社会保険料・生命保険料・地震保険料・市民税額が記載された証明書)の提出が必要です
支給内容
- 小学校新入学者の場合
【支給額】57,060円(お子さま一人あたり)
【支給時期】令和8年3月下旬
【支給方法】市から直接、お支払いします。
- 中学校新入学者の場合
【支給額】63,000円(お子さま一人あたり)
【支給時期】令和8年3月下旬
【支給方法】小郡市立小学校に就学されているお子さまは、令和7年度に就学している小学校を通じてお支払いします。小郡市立小学校以外の小学校に就学されているお子さまは、市から直接、お支払いします。
- 5
モバイルルーターの貸与について
-
小郡市では、市立小・中学生にタブレット端末を貸与するとともに、家庭に持ち帰っての学習に活用していきます。
そこで、インターネットへ接続できる環境を整えることが困難なご家庭に、モバイルルーターを無償貸与することとしました。詳しくは以下をご確認ください。